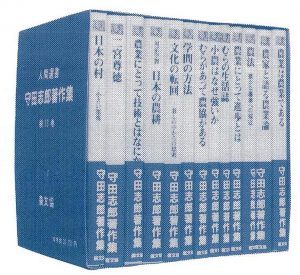��2016�N9��������_�Ǝ咣�u���_�̎g���[�ނ�ɔ_�Ƃ𑝂₷���Ɓv�ł��Љ����c�u�Y�̒���Љ�ł��B
��c�u�Y�@�����ē�
��c����ƈꏏ�ɍl���Ė�����z����
���̈ē���1997�N9�����̌���_�Ɓu�咣�v�̎Q�l�����Ƃ��Č́E��c�u�Y���̒�����Љ�����̂ł��B�\�\�ҏW��
���ނ炪�����Ĕ_��������
�i1967�N�A�Ƃ̌�����s�́w�����Љ�Ɣ_���x1994�N�A�_�����l�ԑI���B��{������j
�u�����قǎ��������Ŏ�������������āA�����đ��l�ɖ��f���������ɒ�������Ă����c�̂��A�ق��ɂ����邱�Ƃ��ł��邾�낤���v�u���̎��͂����ɂ����O�I���B�͂��O���킹�Ă��邠����͂��炭�ӎ��������̂�������������B�v�u�����̋����W�͂��̂悤�Ȑl�דI�Ȃ��̂ł͂Ȃ��v�\�\����Ȍ��t�������ɏo�Ă���{���́A���ɏЉ��w�_�Ƃ͔_�Ƃł���x�̂������O�ɏ����ꂽ���̂ŁA�u�ނ�v�ɂ��Čo�ϊw��Љ�w�Ƃ��������̃��K�l����łȂ��A�����Ɋ�Â��ēǎ҂ƂƂ��ɍl����i�߂Ă����{�B�u��������ƈ������j�I�����@���A�w���{�̑��x�ɂ����Ď�c�����_������������v�i��{������j�y��ƂȂ�����i�ł��B
���_�Ƃ͔_�Ƃł���
�i1971�N�A�_�����B���c������@1987�N�A�_�����l�ԑI���j
���c�����͂��̖{���u�_�w�̌ÓT�v�ƌĂт܂����B
���s��l�����I�������܂����A���܂ł��V�����ǎ҂����܂�郍���O�Z���[�ł��B���[���b�p�_�Ǝ��@���s�ɏo�����҂��A�ߑ�_�Ƃ̐�y�̂悤�Ɍ���ꂽ�ނ̒n�̔_�ƂɁA�y�ɂǂ�����ƍ������������R�ƂƂ��ɂ���l�Ԃ̕�炵���̂��̂����銴�����A���̂܂ܓ��{�̔_�Ƃ��l����v���ƂȂ�A���ǔ_�Ƃ͔_�Ƃł����čH�Ƃł͂Ȃ����A�Ȃɂ��̖��������V�X�e���̎��Ԃ̈�ł��Ȃ��A�_�Ƃ͕�炵���Ƃ������_�ɒB���܂��B
���_�@�\�L���Ȕ_�Ƃւ̐ڋ�
�i1972�N�A�_�����B�����N�Y����@1986�N�A�_�����l�ԑI���j
�w�_�Ƃ͔_�Ƃł���x�ŏq�ׂ���{�I�ȍl������_�Ƃ̓c����{�ɂƂ�����̓I�ȏ�ʂɑ����čl�@��i�߂�{�B
�u�_�Ƃ͔_�Ƃł���v�ƒ��҂������Ƃ��A���̈Ӗ��͂܂��_�Ƃ͍H�Ƃł͂Ȃ��Ƃ����Ӗ��ł���A����ɔ_�Ƃ͎Y�Ƃł͂Ȃ��Ƃ����Ӗ�������܂��B�_�Ƃ́A�Y�Ƃ��̂��̂ł���Ȃ��B��炵�ł��B������H�ƓI�Ȏ�@��Y�ƓI�Ȋϓ_���炷��_�Ƃւ̎w����U���ɂ͋���������ėՂ����Ƒi���A���̂��߂ɁA�_�ƋZ�p���ߑ�Z�p�Ƃ��ĂłȂ��u�_�@�v�Ƃ��čl���悤�Ƃ����킯�ł��B�_�@�Ƃ́A�_�Ƃ̕�炵�̒��ł͂����܂�A�u�ӂƋC�����Ă݂�A�����ɕω����������A�Ƃ����悤�Ȃ��́v�ŁA���������ω��́u�����Ă��Ƃւ͖߂�Ȃ����A�j��I�ȃ}�C�i�X�������炵��������Ȃ��v�B�����Č������ꂪ�u�_�Ƃɂ�����_�ƓI�i���v�Ȃ̂��ƒ��҂͂����܂��B
�u�H�V��L���ɁA�_�@�͂�������͂��܂�v�ȂǁA���ՂȌ������ŏ����ꂽ�{���́A�g�̂ɂ��킹���_�@�ŎY���⒩�s�Ɍ��C�Ɏ��g�ޏ����⍂��Ҕ_�Ƃ̕��X�̎��M��[�߂Ă�������ł��B
������������
�i1973�N�A�����V���ЁA�̂��w���{�̑��x�Ɖ���B2003�N�A�_�����l�ԑI���j
�w�_�Ƃ͔_�Ƃł���x�ɂȂ��炦�Ă����u�ނ�͂ނ�ł���v�Ƃł������ׂ��{�B�ނ������Ƃ����ނ��������A�ǂ݂������̂���{�ŁA�ق�Ƃ��ɁA���҂Ƃ�������Ɉ��K�i���̂ڂ�߂Ă��������ł��B�u�������A�����Ă��鉻�Ƃ��Č�����ςɂƂ�����Ă���Ԃ̎��́A�������ѕ�����K��Ă݂Ă��A�����ɂ��Ẳ������m�邱�Ƃ͂ł��Ȃ������悤�Ɏv���B�����āA�悤�₭�M���Ƃ邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����Ƃ��A�ǂ���玄�͔_�Ǝj�̌����҂Ƃ��Ă̎������̂Ă邱�Ƃ��ł����悤�ɂ��v���v�B�u���{�ɂ�����A�s���Ǝ������鎄�B�̔w�L�͂������ɐF�͂��߁A���̑��͑�n���痣��āA���Ƃ�����Ȃ��ɗV�����邩�Ɍ����Ă���v�u�����܂߂ēs�s�ɏZ��ł�����̂��s���v�ŁA�u���X�����ŕ邵�A�Ă��⋍���◑��\�Y���Ă���_�Ƃ̐l�B��……�s���ɂȂ肻���˂��̂�܂Ƃł��������ƂɂȂ�̂��낤���v���{�ł̕����ɂ���펯�Ɂu�傫�Ȃ܂������v�������n�߂��A���҂̎v���̑傫��������ł��܂��B��ꂽ�u�s���v���A�_�I��炵�̌����ɐS�g�̖����̂��ׂ����o�����Ƃ��n�߂����܁A�{�Ɩ{���̔_�Ƃ̕��X���A�ނ�̐^�������Ĕ������邽�߂ɂ������߂��܂��B�ނ炪�ނ�ł��葱���A�s�s�ƗZ������̂ł͂Ȃ��A�g���邽�߂ɁB
���_�Ƃƌ��_�Ƙ_
�i1974�N�A�_�����@2001�N�@�_�����l�ԑI���j
���j�ƌo�ϊw���̂āA�_�Ɣ_���̐^�������悤�Ɠw�߂Ă������҂́A����͂��͂u��c�_�w�T�_�v�ł��B�_�Ɛ��Y�͘_�A�_�n���L�_�A���Ǝ��{�Ɣ_�ƁA�ނ�̗��j�A�_�@�I�v�l�Ȃǂ��߂����Ĕ_�ƂƂ̘A�����k��ōu�`�����L�^�ł���A�_�Ɣ_���̑S�̑���_���̊�Ŕc�����Ȃ����̂ɍœK�̃e�L�X�g�B�ǂ݂₷���{�ł��B���̖{�̍��k��ŁA��������̎�c�t�@�������܂�܂����B
���ނ�̐�����
�i1975�N�A�������_�ЁB�̂�1994�N�A�_�����l�ԑI���B���R�߉���j
��Ƃ��ē��k�n���̂��܂��܂Ȕ_�Ƃ�K��A�J���ƌ��N�̂��ƁA�H�����̂��ƁA��҂ƔN���A�R�Ɨ��A�����߂����ĂȂǂ����������������B�ʂɈӎ����Ăł͂Ȃ��A�u�����Ă���_���̂Ȃ��Ŗ{���̔_���Ƃ��Đ����Â���v�_���Ƃ��̐����̂Ȃ��Ɂu�������m����……�ߑ�ᔻ�̎���v���A���L����\�\�Ɠ��R�ߎ��͉�����܂��B�u�咣�v�ŏq�ׂ��悤�ɒ��҂�“������Ԃ��Ƃ���”�̍��k���_�Ƃ̐l�X�Ɩ��N�Â��܂����B���̉�ɏo�Ȃ����_�Ƃ�K�˂��L�^�ł��B�L�����̒��̕n���ȂǂƂ悭�����܂����A�����I�ȖL�����Ƃ�����̖L��������̂ɂȂ��Ă���_���̕�炵�̂�������悭�킩��܂��B
����{����
�i1975�N�A�����V���Ё@2003�N�_�����l�ԑI���j
�_���̏o�ł���Ȃ���_�k�ɂ��Ĉ�،�炸�A�S�����ݕ��̓����̂Ȃ��Ɉ�������L���ɂ��悤�ƕK���ɓ������������A������{���ǂ����܂ꂠ�邢�͎��������炪�������Ɠ��̌o�ώЉ�̐��I�̌��҂Ƃ��ĕ`�����������җB��̕]�`���B�q�ώ�`��r���A�����Ɂu���̂Ȃ��ɂ����āA���̔��g�Ƃ��������̊ԕ��ɂ��������̔��g�v�����A���Ҏ��g�̊���������Ȃ��璘�q�����{�ł��B
�����_�͂Ȃ�������
�i1975�N�A�_�����@2002�N�_�����l�ԑI���j
���������Ƃ̈Ӗ��A�_�̉���“����”�A�y�͍앨������A���R�_�@�Ƃ�������A����ɂ�����̂��ƁA������ʂ��Ď��R�ɑ��A�Ȃǎ�Ƃ��Ė{���ɏ��������Ă������҂̔_�@�_�Ƃނ�_�̂��̌�̓W�J�����^�����{�ł��B�u���_���E�̐Â��ȑ��Â����v�Ǝ���ɖ|�M����Ȃ����Ղ��Ƃ��̍����m�ɕ�������ɂ��Ă��܂��B
���҂͋Z�p�҂ł͂���܂���B�������Ƃ������A������Ƃ������A���̖{�͂��ɂ�����������_�ƋZ�p�ᔻ�̏��ƂȂ��Ă��܂��B�u����炢�͔�̍����ȂǂƂ������̂͂Ȃ��B�͔�Ƃ͋�C�̂悤�Ȃ��̂ŁA�ċz�̎d����m��Ȃ��l�͂��Ȃ��B��������Ő[�ċz�������胈�K�̌ċz�@���������肷��B����Ɏ��Ă���v�Ƃ����悤�Ȉӕ\�����_�̗��ĕ��������ς����邨�����낢�{�ł��B
���_�ƂɂƂ��ċZ�p�Ƃ͂Ȃɂ�
�i1976�N�A���m�o�ϐV��ЁB 1994�N�A�_�����l�ԑI���B���i���r����j
��ɂ������w�_�@�x�Łu�Z�p�͐i��ł��A�_�@�͐i�ނƂ͌���Ȃ��v�Ƃ������҂��A���҂̑����Nj��������O�Ō�̍�i�B�_�k���_�ƂɁA�_�@���Z�p�ɂ䂪�߂���ߒ����A���ɂ͓ޗǎ���܂ł����̂ڂ��Đ[���l�������A�Z�p���̂��̂̊T�O���e�ɕύX�𔗂�J��B���܂̋@�B���_�Ƃɂӂ�
“�ǂ�����������”�Ɗ�������ɂ͕K�ǂ̖{�ł��B
���_�ƂɂƂ��Đi���Ƃ�
�i1978�N�A�_�����j
���O���҂��{���Ɋ�e�����_����_������Â̔_�ƂƂ̍��k��ōu�`�����L�^�̂Ȃ�����_�Ǝ��ނɊւ��ďq�ׂĂ�����̂����^�B�i��A�엿�A�@�B�ȂǏ��X�̎��ނ��A�_�Ƃ̔_�k�̎��R�ɂ����ɍ�p���邩�Ƃ����ϓ_���瓴�@�B��L�w�Z�p�Ƃ͂Ȃɂ��x�̘_�_����荡���I�����ɑ����ĉ�͂����{�B
�������̓]��
�i1978�N�A�����V���Ё@2003�N�@�_�����l�ԑI���j
�ӔN�̑�\�I�G�b�Z�C�̂ق���e�u�o�C�v�u����_���̗��j�v�����^�B�o�C��Ղ�K�ˊC�ɋ߂�����s�v�c�����m���A�����̔��@�L�^��_��������ǂ��Ȃ���A�Ō�̌��_�u�c��ڂ͌��͂ɂ���č�炳�ꂽ�v�ɒB����M�̉^�т́A������������������ǂނ悤�ȋ�����ǎ҂ɗ^���܂��B
���Θb�w�K�@���{�̔_�k
�i1979�N�A�_���� 2002�N�A�_�����l�ԑI���j
�_�ƂƂ̍��k��Œ��҂��u�`���A������߂����Ĕ_�Ƃ����_����A���̗��������^���܂����B�Љ�x�j�ɕt�������_�Ǝj�ł͂Ȃ��A�����̕�炵�Ǝ��R�Ƃ̊ւ�肠����y��ɂ����V�������{�_�Ǝj�̍��i���݂���{�ł��B�_�Ƃ̑Θb���M�d�ȋL�^�ɂȂ��Ă��܂��B
���w��̕��@
�i1980�N�A�_�����j
����̊w����A���A��A���̂�����ł��Ȃ��u���̎Љ�w�v�ƋK�肷�邱�ƂŏƊw����ւ�点��V���ȕ��@�����o�����Ƃ����ӔN�̘_�l�W�B�{���ɂ���ēǎ҂́A���҂��Ȃ������̊w����̂ĂȂ���Ȃ�Ȃ������̂��A�u���́v�w����A�����������Ȃ����������Ɠ��������ŕ��������錩���������ɂ��ĒNj����Ă�������m��A�w��̖{���̂��т����������Ƃ�ł��傤�B